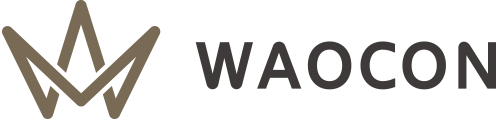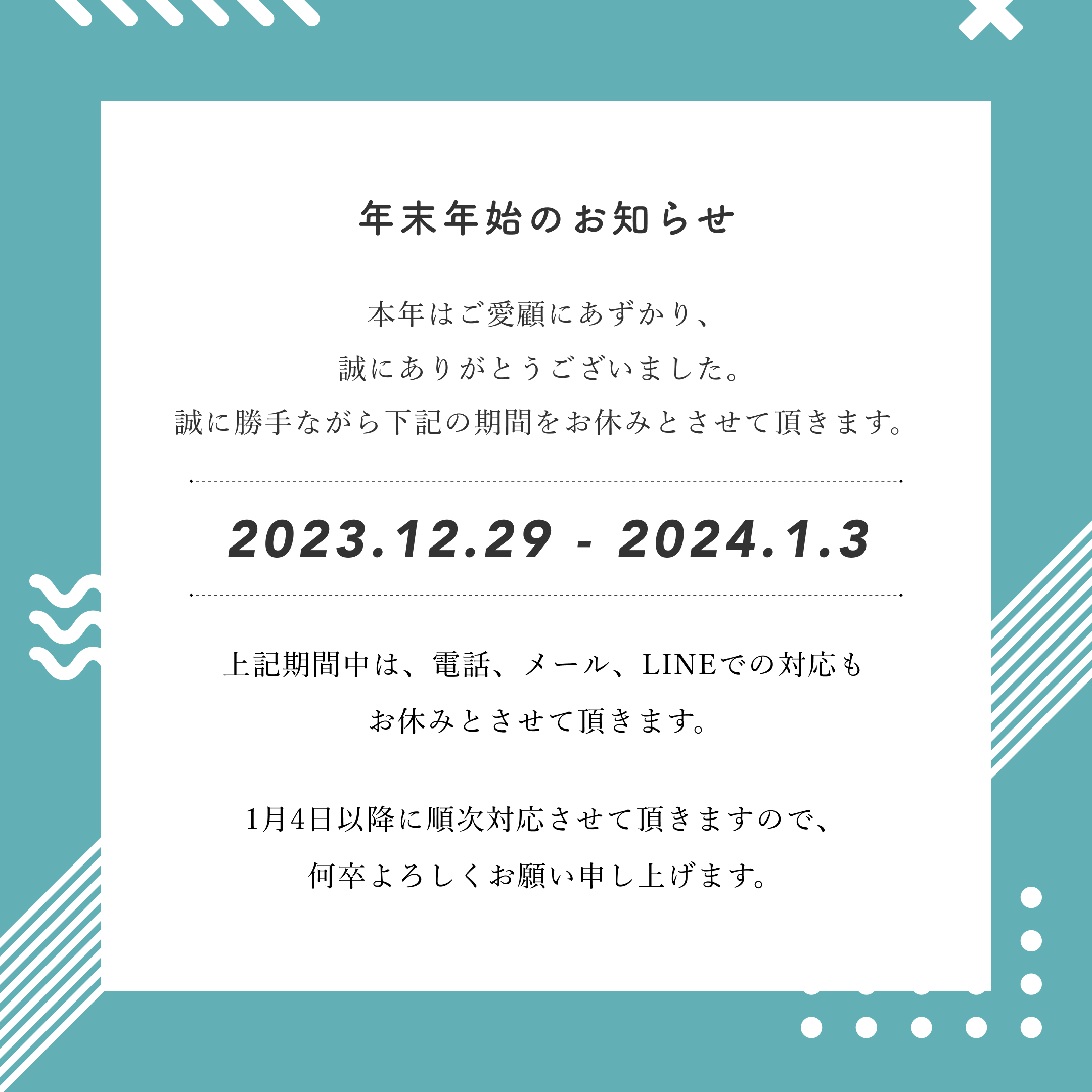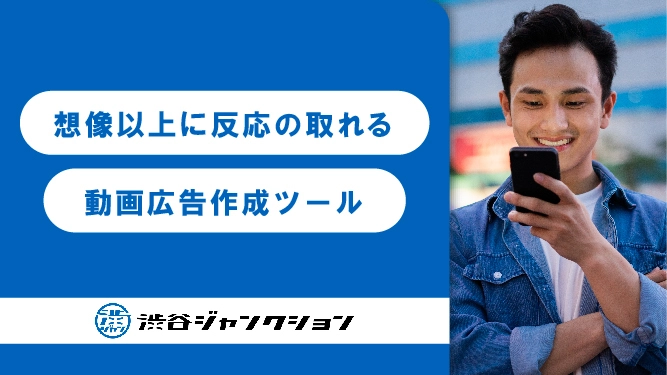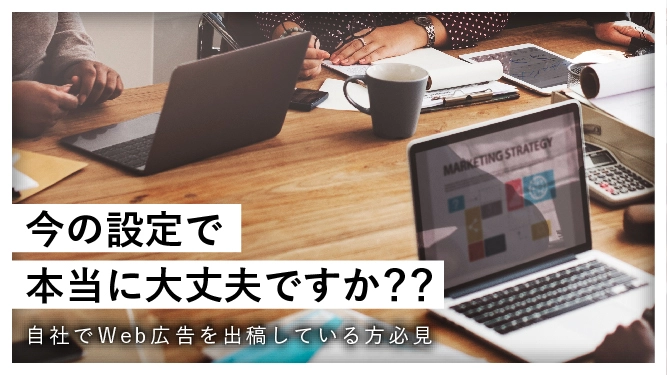【はじめに】
みなさんはコア・コンピタンス分析という手法をご存じですか? ビジネスパーソンの方はご存じの方を多いと思いますが、自社の強みを洗い出し活かすことで、業績向上を図る手法のことです。 幅広い業種に使える手法なので、ご存じの方も今一度、おさらいの意味もこめて、ご一読いただけたら幸いです。【コア・コンピタンス分析とは?】
コア・コンピタンス分析は、「顧客への価値提供を行う能力の他社には真似することのできない中核的な能力」を分析するフレームワークのことを言います。 実際には、他社が真似できない強みを分析するための分析方法で、自社にしか持っていない特有の価値を分析し、それをもとに事業展開をしていくことです。 この手法はコア・コンピタンス経営」は、プラハラッド教授とハメル教授の論文「The Core Competence of the Corporation(企業のコア・コンピタンス)1990年 」によって広まりました。【コア・コンピタンス分析の目的】
■自社の強みを明確にできる コア・コンピタンス分析を行うことで自社の強みを明確にしていくことができます。 コア・コンピタンス分析では、様々な競合他社と比較しながら自社の強みと弱みを見出していくような方法になっています。 そのため、常に市場で戦っている他社と比較しながら分析を行うことができるので、市場にあった強みを見つけることができます。 この強みを見つけることが出来れば、セールスの時に自社の強みを最大限に活かしたり、戦略の拡大を見込んだロードマップを作製することができます。 ■各社の強みを知ることができる 分析の際、競合他社や関連会社などを比較対象として分析を行うので、市場で戦っている競合他社の強みも知ることができます。 競合他社の強みを知ることで、最も争ってはいけないところを明確にすることができ、競合他社と直接競い合うことを事前に回避し、リスクを下げることができます。 さらに、競合他社の強みを知ることで「自社の戦略をどのようにすればいいのか?」 ということも考えていくことができるので、今後の戦略を考える上でも有益な情報になりやすいです。 ■市場を知ることができる 複数の会社を比較して分析を行うことで、 自社が戦っている市場を明確にしていくこともできます。 どのような企業が成果を上げて、「何が違うから差がついているのか?」明確にしていくことで、会社の違いを知ることだけでなく、市場が求めているものを把握することができます。 そうすることで、今まで意識していなかった新たな市場に気づくこともできるので、自社の可能性を広げることができます。 以上のような目的を達成することができるからこそコア・コンピタンス分析は現在でも活用され続けています。
【コア・コンピタンスを分析するポイント】
■模倣可能性(Imitability) 模倣可能性とは、「競合他社に簡単に模倣できるものか」という視点です。模倣可能性が低いほど模倣が困難になり、他社がまねしづらく競争優位性は大きくなります。 とても素晴らしいサービスで、かつ、大きく市場を占有していても、そのサービスが誰でも作れるようなものであった場合、他社との競合が増えてしまいます。 そのような事態になってしまうと自社の利益が落ちてしまい、市場のシェアも手放すことになってしまいます。 そのため、コア・コンピタンス分析をする際は、自社のサービスが高い専門性があるものであるか、技術力があるかなどの分析をすることが非常に大切となってきます。 ■移動可能性(Transferability) 移動可能性とは、「1種類の製品や分野だけでなく多くの製品や分野に応用ができ、幅広く展開できるか」です。 移動可能性が高いほど、他分野でも競争優位性は大きくなります。移動可能性というのは、「そのサービスがいかに汎用性があり、様々なサービスやアイディアに応用が効くか」ということです。 移動可能性が高いと、市場でそのサービスが使える機会が増えることになるので、必然的に価値が高まるということになります。 ■代替可能性(Substitutability) 代替可能性とは、「他の方法で置き換える事の出来ない唯一無二の存在であるか」という視点です。当然、代替可能性が低いほど、他の物で置き換えられない絶対的な存在となります。 代替可能性とは、分析対象のサービス(事業)以外でも、ニーズが満たされてしまう可能性があるか?ということです。 ■希少性(Scarcity) 希少性とは、「その技術や特性が珍しいものであり、希少価値が存在するか」という視点です。希少性が高いほど、強い武器に成長する可能性が高いと考えられます。 こちらの希少性は文字通り、分析対象のサービスに稀少性があるか?を分析するということです。 この希少性が高いと消費者側としては、「どうにか手に入れたい!」という心理状態になり、そのサービスや製品はそのプレミア感がさらに新しい顧客を生み出すという好循環を回せるというメリットがあります。 現在はSNSが発達した結果、爆発的に情報が拡散され一気に新規ユーザを獲得することで、相対的に希少性が高くなる現象も見受けられます。 ■耐久性(Durability) 耐久性とは、「その強みが長期にわたって競争優位性を維持する事が出来るか」という視点です。耐久度が高いほど、コア・コンピタンスの価値が保証されることとなります。 耐久性は、長期に渡って市場での優位性を保ち続けられるか、ということになります。 こちらはブランド名や名声がある場合は耐久性が高いと言われています。 この耐久性に関しては変化の激しいIT業界、特にゲーム市場において重要となってきます。耐久性を常にキープし続けるためにゲーム内でのイベント、アニメとのコラボなどを定期的に行っている様子は、幾度となく見ているのではないでしょうか?【まとめ】
今回はコア・コンピタンスの重要さについて記させていただきました。 己を知り、相手を知ることは非常に大切なことです。 コア・コンピタンス分析を実践することで、一歩ずつでも自社の強みを発揮してシェアを拡大することができると信じています。 また、情報を収集するという事は、企業の成長方法を読み解くという事でもあります。 顧客のニーズに寄り添う経営は、企業をより豊かなものにするでしょう。 最後までお読み頂きありがとうございました。